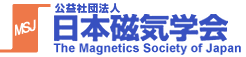26.03
- 分野:
- 磁気物理、スピントロニクス
- タイトル:
- 分子関連の国際会議における分子スピントロニクスの最新動向
- 概要:
- 7月1日-8日の日程でダブリンにて開催された分子関連の国際会議(ICSM 2006)において、今回新たに分子スピントロニクス・分子磁性のセッションが設けられた。その中から関心を集めたいくつかの分子スピントロニクス・分子スピン素子に関連する発表を紹介する。
- 本文:
- 今回開催されたInternational Conference of Science and Technology of Synthetic Metals(ICSM)は2年に1回開かれる国際会議であり、有機エレクトロニクス・有機超伝導体・有機発光素子・ナノカーボン素子・有機伝導体など広範な領域をカバーする分子関連で最大の国際会議の1つである。昨今の分子スピントロニクスへの関心の高まりを反映してか、分子スピントロニクス・分子磁性のセッションが設けられ活発な議論が行われたので、いくつかを紹介したい。
招待講演には2004年にCo/Alq3/LSMOというサンドイッチ構造を用いて11 Kで40 %程度の磁気抵抗(MR)比を観測したユタ大のVardenyが登壇し、この研究成果の詳細や最近の進展などを網羅的に話した。注目されるのはSAM(self-assembled molecule)膜のサンドイッチ構造においても4 Kではあるが数十%のMR比が観測された、という部分であり論文の掲載が待たれる。但し、以前より議論の的となっている金属/分子界面が綺麗に形成できず、MRの起源や再現性が曖昧である、という問題に関しては新たな説明はなく、SAM膜で観測されたMRの起源や再現性などはcontroversialなままであり続ける可能性がある。
一般講演で注目されたものでは、まずEpstein(Ohio州立大)やWohlgenannt(Iowa大)らが近年報告している、非磁性金属電極で有機分子を挟んだ構造においても室温で発現するanomalousなMR効果が挙げられよう。未だにその起源について確たる理論はないものの、96年ごろから有機分子薄膜の抵抗が磁場印加によって変化することが知られていた。今回の彼らの報告ではAlq3やpolyfluoreneなど様々な材料を対象に薄膜構造(アモルファス)を用いてこのMR効果の研究を行い、統一的に説明できる理論の構築を目指している。内容の詳細であるが、印加磁場100 mT程度の範囲で最大で15 %程度抵抗は変化する。低温になるほどMR比は小さくなり、またMR比のバイアス電圧依存性は単調に変化(増加するか減少するかは材料に依存する)する。中にはMR比の符号がバイアス電圧によって反転する材料も存在する。本質的には材料そのものの磁気抵抗であると思われるが室温でもかなり大きなMR効果が発現することは面白みであろう。
他にも室温における磁気抵抗効果の観測に関する報告は2件あった。1つは筆者らのグループの報告で、C60-Coナノコンポジット系における室温でのスピン依存伝導の観測に関するもの(JJAP[Express Lett.] 45, L717 (2006)に既報)、もう1つは東北大多元研の生駒らのグループで光励起によりPoly(N-vinylcarbazole)中にスピンを励起し室温でGMR効果を観測した、というものである。このように室温での磁気抵抗・スピン依存伝導の観測が徐々に報告されるなど、分子スピントロニクス分野もいよいよ離陸寸前の様相を呈してきたように思われ、この分野に携わるものとしても嬉しい限りである
(阪大院基礎工 白石誠司)
Ⅰ